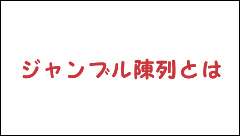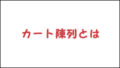商品の陳列方法には様々な方法がありますが、その1つにジャンブル陳列と呼ばれるものがあります。
ジャンブル陳列とは、陳列棚(ゴンドラ)最下段がワイヤーバスケットというカゴの構造になっている部分や移動ができるキャスター付きのバスケット、籐製(籐風)のカゴに商品を投げ込んだイメージで陳列をする方法です。
この記事では、ジャンブル陳列の特徴やスーパーマーケットの売り場の中でよく使われる場面を紹介しております。
ジャンブル陳列の特徴
商品を投げ込んだ感じで積み上げて陳列をすることで、ボリューム感を演出することができます。
さらに、このボリューム感からお客さんにお値打ち感を感じてもらえる効果もあります。
また通常の陳列とジャンブル陳列を組み合わせることで、売り場にアクセントをつけることが可能です。
冒頭で投げ込むという点を紹介しましたが、カゴにガンガン商品を放り投げることはしません。来店したお客さんから見ても心証はよくありませんしね。実際はカゴの中に商品を置いていくようなイメージで作業をします。
ージャンブル陳列を行っている画像ー
赤線で囲っている箇所がジャンブル陳列です。

ーキャスター付きバスケットの例ー
ー籐風のカゴの例ー
よく見るのはカップ麺売場
下の画像はカップ麺売場でジャンブル陳列を行っているものです。

スーパーのカップ麺売場に行くと上段や中段はいわゆる普通の棚だが、下段だけがカゴの構造になっていて、そこにカップ麺の向き(フェイス)を揃えることなくランダムに投げ込んだような感じで置かれているの見たことがあるはずです。
上段・中段と下段では、棚の構造が異なり売場のアクセントになります。また下段のカゴ部分が前に飛び出ているため、少し遠くの通路を歩いているお客さんでも目にとまりやすいという特徴があります。
ジャンブル陳列のメリットとして、商品補充をする作業時間が短くなって作業効率がよくなると一般的に言われています。私の勤務する店舗のカップ麺売場も最下段がカゴの構造となっています。
先入れ先出しをするために、カゴに残っているカップ麺を先に取り出して一旦カートやケースに置いておき、日付の新しいカップ麺をカゴ内に置いていき、最後に取り出していたカップ麺をのせていく作業をするため、あまり作業時間は短くなりません。個人的にはさほど作業時間は変わらない印象です。
キャスター付きのバスケット・籐製のカゴへの陳列
キャスター付きのバスケットと籐製(籐風)のカゴへのジャンブル陳列は、お客さんを引き寄せる効果があります。主に次の場面で利用されます。
キャスター付きのバスケット・・・店内の通路上や入口を入ってすぐの催事売場
籐製(籐風)のカゴ・・・店内の角(通路が交わる箇所)やエンド中央、入口を入ってすぐの催事売場
キャスター付きのバスケットや籐製のカゴへ商品を陳列する際は、ボリューム感を出すためにカゴの底に箱を置いてかさ上げをしたり、袋物の商品については袋をピンと張ったり、手でならして形を整え高さを揃えるなどの作業が出てきます。
さらに他の什器を組み合わせて陳列するなどそれなりに手間がかかります。またカップ麺の陳列と違って、ランダムに陳列するのではなく商品の向き(フェイス)を揃えて陳列をするケースがほとんです。普通に陳列をする場合と比べて作業量が多いです。
品出しの作業をする側としては、ジャンブル陳列を行うより普通に陳列をするほうが正直楽ですね。
―陳列の基本的なテクニックを解説している本の紹介ー